文字こそが想像力の使者
2026.02.10
文字を読むこと、皆さんは好きですか、嫌いですか。文字というものは、人間だけが持つ特殊能力です。地球上のあらゆる動物の中で人間だけが持つ特技なのであります。本来、話す、聞く、書く、読むという能力が、人間には備わっており、人間として大事なコミュニケーションを司っているのです。その中でも、聞く、話すというツールは、直接的な意思表現には欠かせないものであり、いわゆる会話というものです。この特性は、お互いが理解しあうための大切な技能なのであります。聞く、話すというのは、人間が生まれて一番目に身につく能力でもあります。生まれた赤ちゃんの人生の第一歩なのです。そこから年齢を重ねるにつれ、書く、読むという能力が備わっていくのです。聞く、話すという行動は、本来持ち合わせる脳が受け入れて、会話という形態に仕上げていきます。ところが、書く、読むという能力は、いくら天才であっても自分一人では、到底備わらないものなのです。日本人で言うならば、ひらがな、数字、漢字、現代ではアルファベットも必要です。これらは、自分以外の人に習い、覚え、活用しなければなりません。次に文字を覚えると同時に、書くことが出来るようになっていきます。そして、繰り返し書くことによって覚えるべき文字を増やしていくわけです。そうして覚えた文字たちは、自己表現に大きく役立っていきます。学校教育を通じて大方の人間は、聞く、話すに加えて、書くことによって自己表現をしていくわけです。文字を覚えていく段階では、テストという方法で理解度を図ります。そして、年齢を重ねていくと、自分の興味があること、したいことに対して言葉だけではなく、論文や書籍による筆記という方法で前進していくのです。それが数学であっても物理であっても、化学や科学であっても文字が必要となります。言い換えれば原始の時代から文字というものが、人間の進化に最も必要なツールであったわけです。そんな文字が近ごろ劣勢なのであります。例えば新聞。紙に印刷された文字を読む習慣が、どんどん減少しているのです。デジタル紙面というものを、どの新聞社もネット上に公開してパソコンやスマホの画面で読むことはできます。これはまだ、文字を読むという部分では、従来の新聞紙と変わらないのでありますが、某IT企業などが販売している、書籍を音声で読ませるというものが現れています。私も試してみたのですが、どうもいけません。なぜか。眠気が襲うのです。書籍、特に小説というものは、読みながらその場面、状況、風景を自分なりに想像を掻き立てながら小説の現実に入り込むわけです。これは、十人十色で人それぞれのシーンが出現していると思うのです。例えば、「吾輩は猫である」を読んだ時、その猫は、三毛猫か、黒猫か、白猫か読み手によって、そのファーストインプレッションは違うと思うのです。ところが、映画やテレビドラマで見てしまうと、そこで現れる猫の一択になってしますのです。小説とはそもそも、読み手の好奇心と想像力をわしづかみするものであり、どんどんとその小説の世界に引き込まれてしまうものです。もう十数年前に読んだ村上春樹氏の「1Q84」という小説は、現実と非現実が幾重にも交錯する小説でしたが、最高に想像を掻き立て、没入してしまう展開でありました。ミリオンセラーであったと思いますが、確か、映画にはなっていなかったと記憶しています。本当にそれでよかったと思います。なぜなら、この作品こそ、読み手それぞれの想像の世界に、自分だけの世界に没頭してほしいと思うからです。自分は、東野圭吾氏の大ファンなのですが、彼の小説は、たびたび映画になります。この場合もだいたい先に小説を読んでいます。そして映画も見るのですが、小説を読んだ自分の想像の世界が絶対素敵なのです。もちろん、映画の世界も大好きなのです。自分なりの解釈で見ることが出来るからです。映画の場合は、自分が主役なのです。ただ、映画の場合は、見る、聞くが主体になります。小説ほどのイマジネーションは残念ながら湧いてこないのです。「文字を読む」何気ない所作ではありますが、人間が司る最大の能力ではないでしょうか。本を読もう!好奇心を込めて。
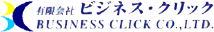
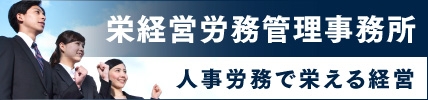
 お問い合わせ
お問い合わせ 06-4308-2700
06-4308-2700